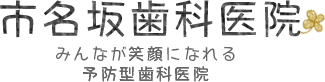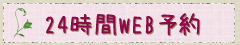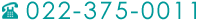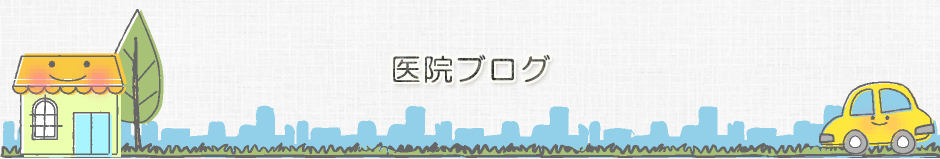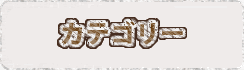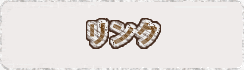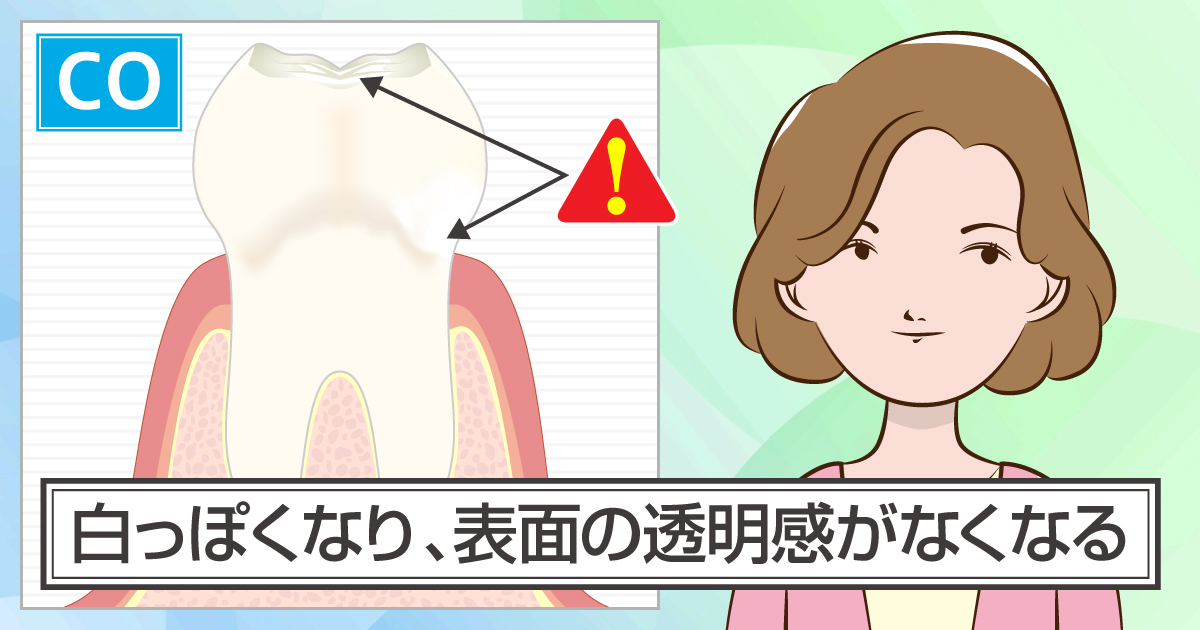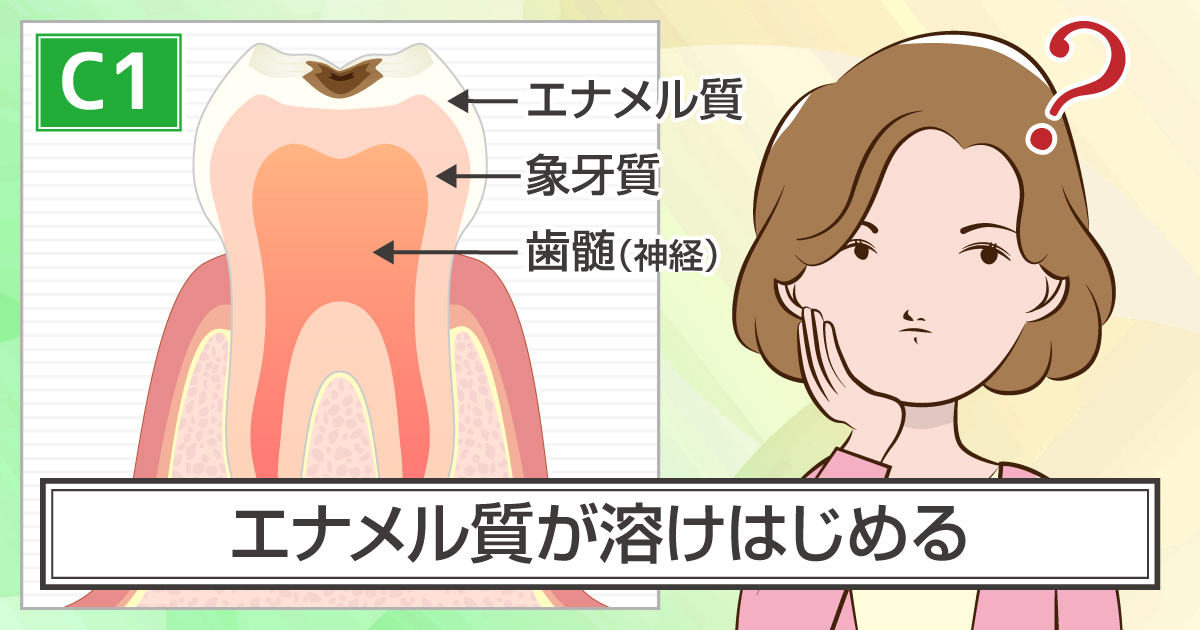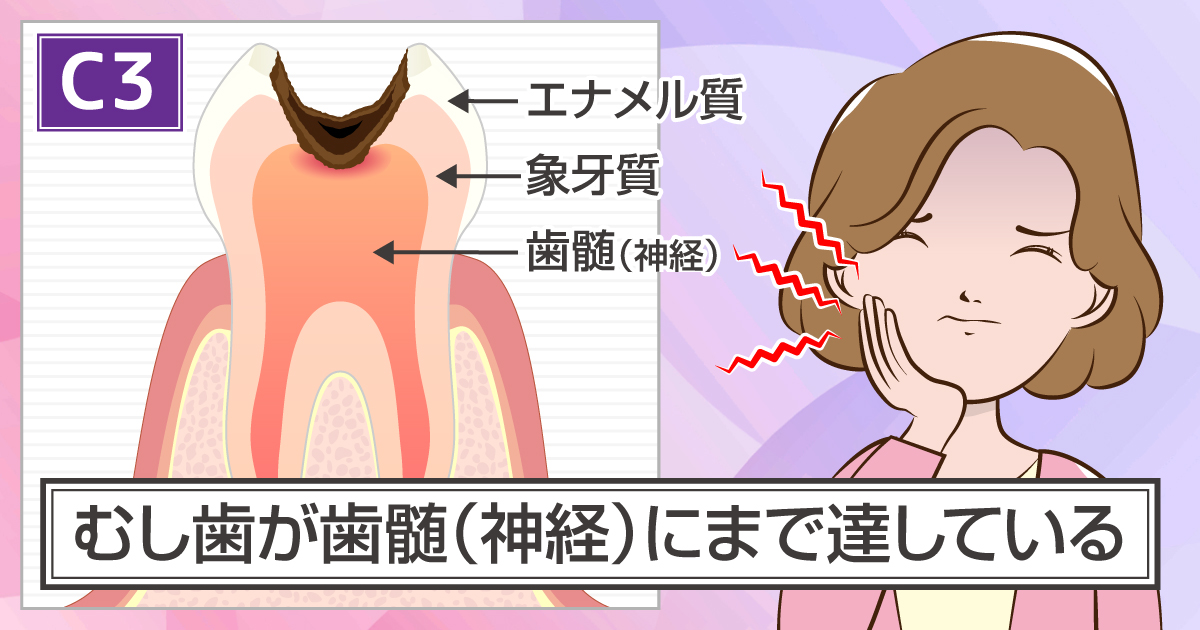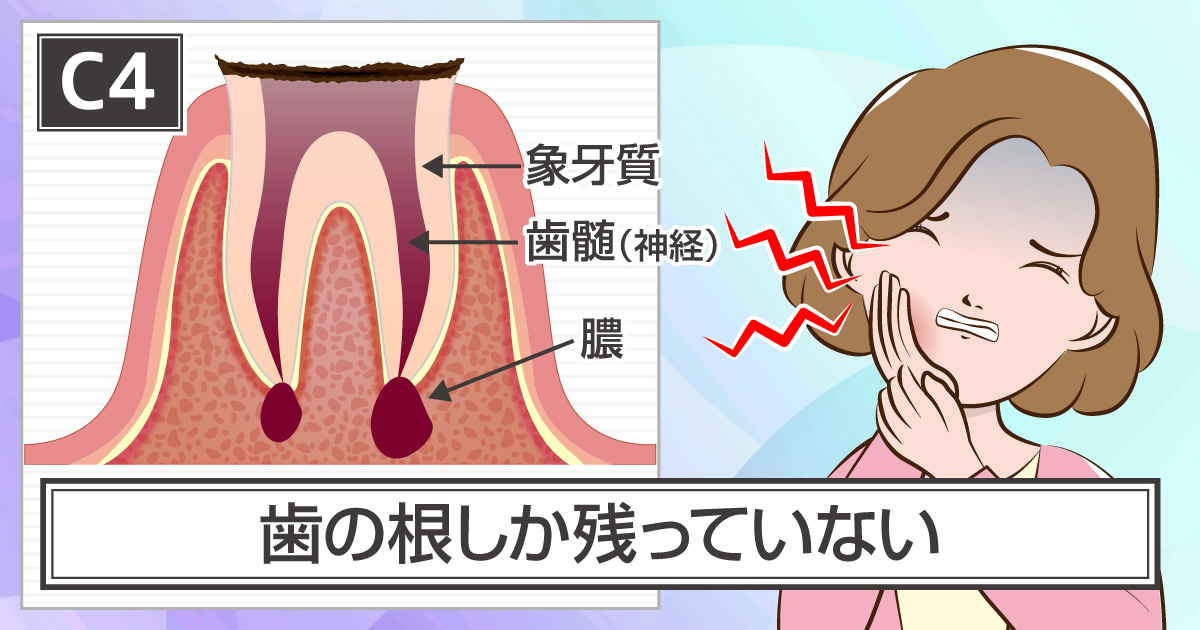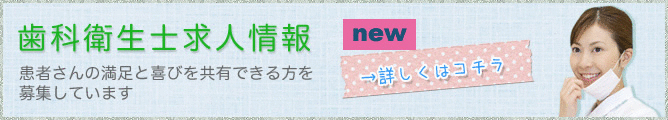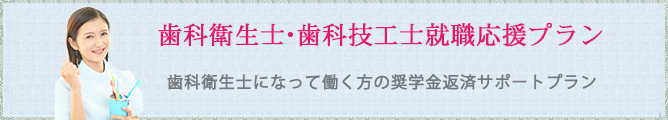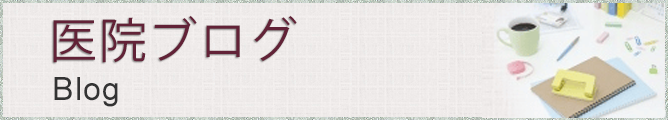新米パパ・ママ必見!妊娠中に増えるお口のトラブル

こんにちは。院長の佐藤です。
11月23日は年内最後の祝日、
「勤労感謝の日」ですね。
文字からすると
「働く人に感謝する日」だと思われがちですが、
実はそれは少し違います。
この日は
勤労を尊び、
生産を祝い、
国民がたがいに感謝しあう日
つまり、
「『働くこと』そのものに感謝する日」なんですね。
今年最後の祝日を、
日頃がんばっているご家族や自分へのご褒美として
ゆっくり過ごしてみるのはいかがでしょうか。
さて、そんな「勤労」といえば、
近ごろは男女関係なく仕事をしている人が多く、
なかには、妊娠中でも働くお母さんもいらっしゃいます。
しかし、妊娠中の身体には様々な変化が起こるため、
今までのようにいかないこともたくさんあります。
そしてそれはお口の中でも同じ。
皆さんも、
「妊婦さんは、むし歯や歯周病になりやすい」
といった話を聞いたことはないでしょうか?
今回はそんな妊娠中に増える、
お口のトラブルについてご紹介します。
◆妊娠中はお口のトラブルの悪循環に注意!!
妊娠すると女性ホルモンが増加します。
実は、歯周病を引き起こす歯周病菌の中には
「女性ホルモンによって活発化」するものがあり、
歯周病のリスクが増大します。
すると、歯ぐきに腫れや出血がみられるようになり
さらに、お口の中がネバネバするなど
不快な状態になることが少なくありません。
また、ホルモンバランスが乱れると
「妊娠性エプーリス」という病気になり
歯ぐきに「できもの」ができることもあります。
これらはいずれも、
「痛み」や「出血」を伴うため、
歯みがきしづらくなります。
すると、
お口の細菌がどんどん増えることになり、
歯周病がさらに進行して、
もっと腫れや出血がひどくなる…。
こうした悪循環になってしまうのです。
もちろん、細菌が増えれば歯周病だけでなく
むし歯の危険性も高まります。
◆母体だけじゃない!
歯周病は赤ちゃんにも影響が…
さらに、歯周病はお口の中のトラブルに留まらず、
赤ちゃんにも影響を及ぼします。
歯周病はお口の中だけでなく、血管内に細菌が入り込んで
全身に影響を及ぼします。
実は、妊娠中に歯周病になると
「低体重児・早産のリスク」が高くなる
ということが明らかになっているのです。
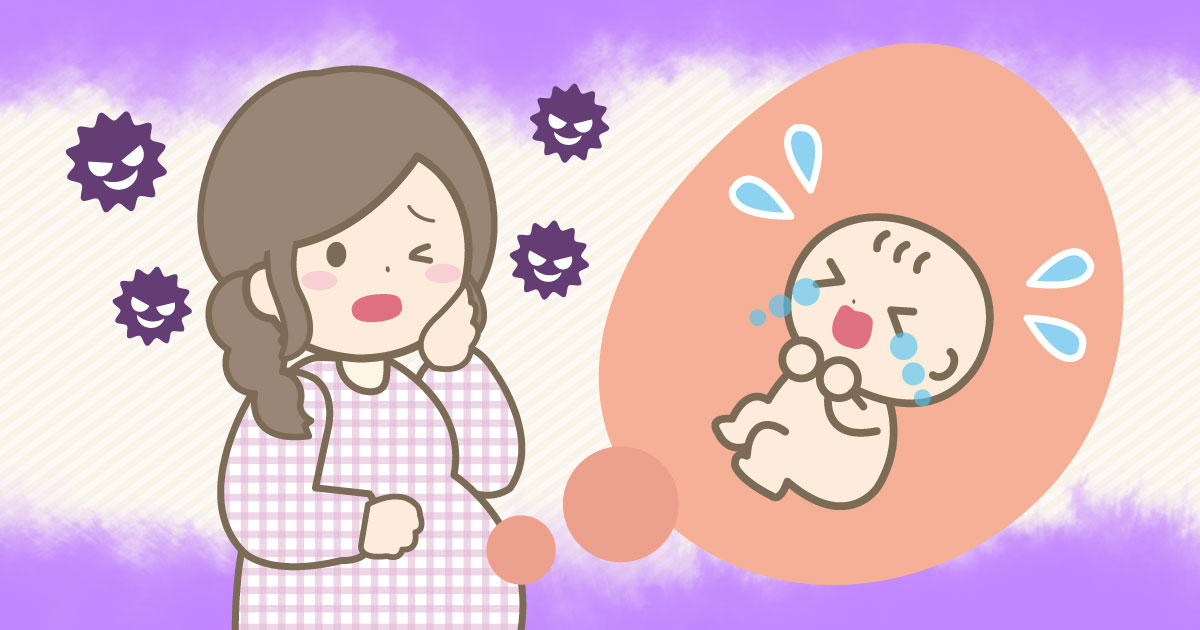
日々の歯みがきは、歯周病予防の基本!
ですが、
妊娠中はつわりがひどいと
歯みがきが難しいこともあります。
そんな時は、
・歯みがき粉の味を変える
・洗口液を使う
それも難しければ、
うがいをするだけでもいいので、
お腹の赤ちゃんを守るためにも
お口を可能な限り清潔に保つように
心がけてみてください。

◆妊娠中でも治療はできる?
妊娠中の歯科治療というと、
赤ちゃんへの影響を気にして
治療をためらうお母さんもいらっしゃいます。
しかし、病気を放置していると
お母さんのストレスが増えたり、
低体重児・早産のリスクが高まったりして、
かえって悪影響を与えることも。
そのため、しっかり治療するほうが
赤ちゃんにとってもお母さんにとっても、
確実にメリットがあります。
安定期に入れば、
ほとんどの治療を受けていただくことができますし、
麻酔やレントゲンなども
胎児にほぼ影響はありません。

また、安心してお産に臨めるよう、
妊娠初期と安定期には
歯科検診を受けましょう。
心配事などのストレスは溜め込まないように、
気になることがあればいつでもご質問ください。
市名坂歯科医院
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田3-14
TEL:022-375-0011
URL:http://www.ichinazaka-dc.com/
Googleマップ:https://g.page/r/CSXgMeYScZNaEAE?gm