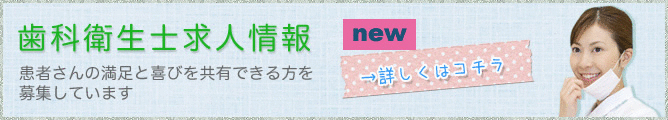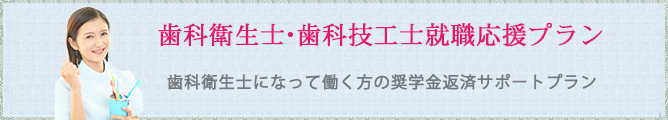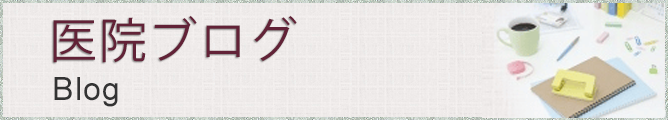キシリトールQ&A①
皆さんこんにちわ.gif)
最近はすっかり寒くなり、風邪やインフルエンザに注意が必要な時期になりましたね。
コロナ対策のマスクや手指消毒は風邪予防にもなりますので、徹底しましょう.gif)
今回は、キシリトールについてです。
市販のキシリトールガムを食べたことがある方は多いと思いますが、そもそもキシリトールって何なのかご存知ですか?
また、虫歯予防に効果が出るためにはキシリトールをどのくらい摂取すると良いか知っていますか?
今回はキシリトールについて基本的なことをQ&Aでまとめてみました。
Q1.キシリトールってなに?
A1.キシリトールは白樺や樫の木などの原料からつくられる天然素材の甘味料です。
糖アルコールと呼ばれる炭水化物の一種で、お砂糖と同じくらいの甘さがあります。カロリーはお砂糖よりちょっと少なめです。
Q2.キシリトールにはどんな効果があるの?
A2.キシリトールはお砂糖と同じくらいの甘さがあるのに、虫歯の原因となる酸を作りません。
さらに、虫歯菌を減らして歯を丈夫にする効果があるので、虫歯を防ぐために多くの国で積極的に活用されています。
≪キシリトールの効果≫
・プラーク(歯垢)を作る材料にならない
・酸を作らない
・プラークの量を減らし、歯磨きで落としやすくする
・ミュータンス菌を減らす
・再石灰化を助ける
→キシリトールの甘さで唾液が沢山出る
→唾液中のカルシウムを安定させて、歯に運ぶ働きがある
Q3.お砂糖と同じように甘いのに、なぜキシリトールだと虫歯にならないの?
A3.ミュータンス菌は糖をエサにして、プラークと酸を作ります。
しかし、キシリトールはミュータンス菌のエサにはなりません。
それでも、ミュータンス菌はキシリトールを取り込むことを繰り返しますので疲れてしまします。
その結果、ミュータンス菌の活動は弱まり、数が減っていくのです。
Q4.キシリトールは食べ物にも含まれているの?
A4.キシリトールはイチゴやラズベリーなどのベリー類、プラム、カリフラワー、ほうれん草、レタスなど身近な食べ物にも含まれています。
例えばイチゴだと乾燥重量100g中に300mgほどのキシリトールが含まれています。
ただし、虫歯予防に必要な量は5~10gとされていますので、食べ物だけで摂ろうとしても十分ではありません。
虫歯予防のためには、ガムやタブレットなどから摂るといいでしょう。
今回は以上です。
またの機会にキシリトール摂取についてまとめたいと思いますので、また読んでくださいね![]()


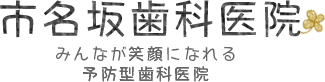
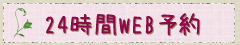
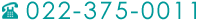
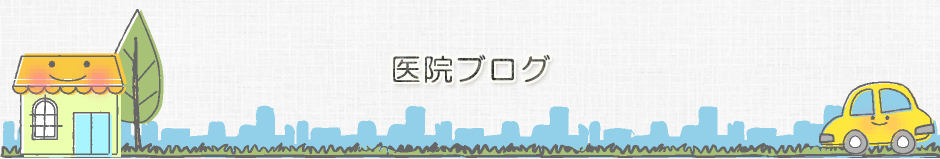

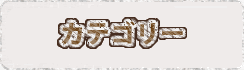
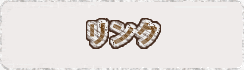


.gif)
.gif)
.gif) 『進行した虫歯は自然には治らない』
『進行した虫歯は自然には治らない』.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)