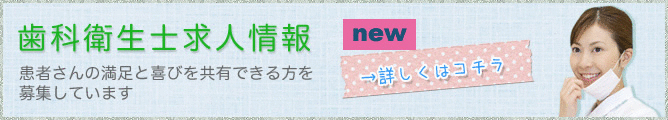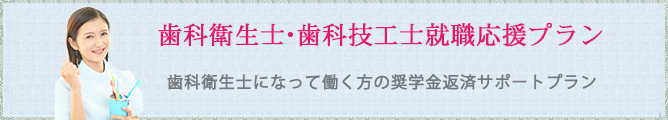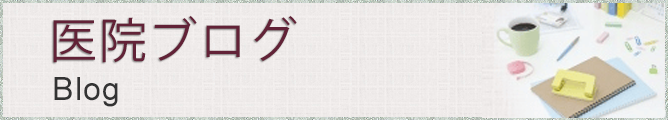欠損放置
皆さんこんにちは![]()
残暑も厳しく、過ごしやすい秋が待ち遠しいですね.gif)
さて、今回は歯が抜けたままになっていると・・・というお話です。
むし歯や歯周病、事故などの損傷で、1~数本程度の歯を失ってしまった場合、
それ以上歯を失ってしまわないよう、注意が必要になります。1~数本失って
しまった場合、ブリッジや義歯などで、失った部分を補うようになりますが、
その、欠損部を補うために入れたはずのブリッジや義歯によって、更に歯を
失ってしまうリスクが高まることになります。
ブリッジの支台となる歯や、義歯のバネを掛ける歯には、過度の負担がかかる
ためです。そうならないためにも、ブリッジや義歯を入れた場合には、それまで
以上の予防とケアが必要となります。
また、そういうリスクを避けるためにも、インプラント治療は有効になりますので
1つの選択肢として、考えてみるのも良いと思います。
歯の欠損を放置したままにしていると、様々なリスクが生じてきます。
★隣在歯の傾斜(隣の歯が失った歯の方向へ倒れ込んでくること)、対合歯の
挺出(咬み合わせる歯を失ったことにより、失った歯の方向へ歯が出てくること)が
起き、さらにこれにより、咬み合わせも変化してしまい、顎関節にも悪影響を及ぼします。
また、前述のように、1本の歯を失うことにより、多数の歯を失うリスクも高まります。
★咀嚼能力の低下により、脳の認知領域の変化が起こり、認知症の発症を引き起こすことが
あります。
★ADLの低下を招き、免疫能力低下、嚥下機能低下により、肺炎に掛かりやすくなります。
★1本歯を失うごとに転倒のリスクが高まっていき、65歳以上で、残りの歯が19本以下の
方は、転倒のリスクが2.5倍になります。高齢の方の場合には、転倒により大腿部骨折
などしてしまうと、それがきっかけとなり、寝たきりになってしまうことがあるので、
特に気を付けなければいけません。
★20本の歯が残っている人は、食事を「おいしい」と感じられるそうです。逆に、11本
程度しか残っていない人は、食事を「おいしくない」と感じるそうです。
欠損歯を放置している場合、「1本2本無くても、大して困らないから」などと放置せず、
何らかの方法で、バランスよく咬めるようにすることが大事になります。
不幸にも、1本の歯を失ってしまったとき、それにより、これから起こりうるリスクを
考え、次々と歯を失ってしまうことに繋がらないように、最善の方法を考えていきましょう。


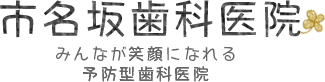
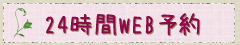
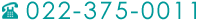
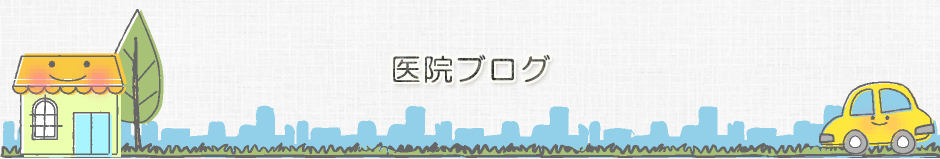

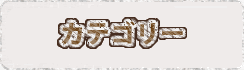
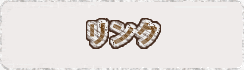


.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)