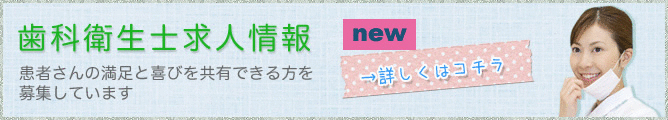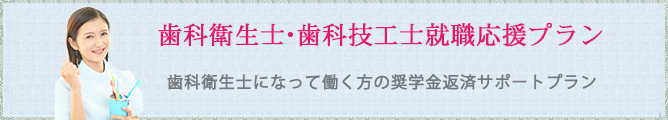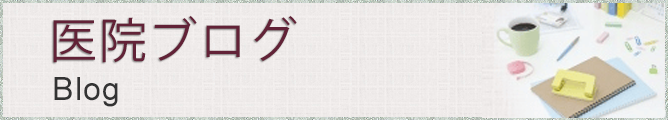口呼吸の弊害と鼻呼吸
この時期早くもインフルエンザが流行.gif) しはじめていますが
しはじめていますが
風邪をひきやすい方、.gif) ひきにくい方がいらっしゃいます
ひきにくい方がいらっしゃいます
日本病巣疾患研究会の今井一彰氏のコラムを読ませていただきました。
私は歯科医院で働いている立場で
口呼吸でだと むし歯になりやすいとか、
歯肉炎(歯周病)を悪化させたり
歯列に影響をおよぼしたり、
口が渇く(ドライマウス)が原因の口臭が強くなったりなど
認識はしていましたが
そればかりではない、口呼吸の弊害について勉強になりました。
紹介させていただきます。
はじめに呼吸について
呼吸とは酸素を取り込み、二酸化炭素を排出すること
私たちは二つの呼吸を行っています。
一つ 鼻呼吸法 鼻で吸う息、吐く息両方行う呼吸法
二つめ 口呼吸法 吸う息、吐く息のどちらか一方でも口から行う呼吸法
*常時開口状態に口唇閉鎖不全(いわゆるポカン口)も含む
口呼吸になる理由
軟らかい食(口の周りの筋肉が発達そないため)
言葉の変化(メールなどで会話をしなくても意思を伝えられる)
口遊びの減少(口笛を吹けない人が多数)
アレルギー疾患の増加(花粉症、アレルギー性鼻炎でますます口呼吸に)
急激な温度変化(血管作動性鼻炎や、暑さ寒さの刺激による口呼吸)
激しい運動
就寝中のいびき
携帯ゲーム、スマートフォンの操作に集中している時
などたくさんの原因が挙げられますが、一つまたは複数絡み合っている場合もあります。
そもそも数いる哺乳類の中で、いつも口で息が出来るのは人間だけです。
これは、しゃべる機能を獲得できたからと言われているそうです。
素晴らしい進化ですね。
口呼吸によって引き起こされる病気
小児期 アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎、気管支炎
歯並びが悪くなったり、むし歯
鼻閉により、集中力や学力が低下など
この時期にしっかりと対策を立てておく必要があります。
その他慢性扁桃炎を繰り返してしまうことによる
IgA腎症の発症に繋がることもあるため注意が必要
成人期 小児期からの疾病が引き続いていることがあります
うつ状態になる、やる気が起きないといった
精神症状を見ることがあります。
色々な病気に関係していると言われている歯周病も、
口呼吸によって悪化しましす。
風邪をひきやすい、扁桃が腫れやすいと
学業、仕事に与える影響も大きくなります。
老齢期 ドライマウス、いつも口が渇くという症状が出てきます。
その他誤嚥性肺炎など口腔や咽頭筋力の低下により
起動抵抗の高い鼻呼吸がいらくなり、口が開きやすくなります。
呼吸は一日のうちで何万回もしています。ご飯を鼻から食べる人がいないように
空気も口から吸うことは良くありません。
そのちいさな間違いが積もり積もって大きな病気を引き起こすことがあるようです。
口呼吸の疫学
口呼吸による弊害はどれくらい存在しているのでしょうか。
幼児を対象にした研究で、保護者からの申告では21%に口呼吸が認められ
これが小学校高学年を対象にした専門家の診察ではその割合が倍以上程度に達します。
お子さんが口呼吸による問題を起こしていないか、専門家に診てもらうのが望ましいようです。
口呼吸は自覚していない場合も多いようで、
例えば10歳の女の子
口唇乾燥・上顎前突(出っ歯)開口(かみ合わせが悪い)
扁桃腺肥大・口蓋乗反射消失(のどちんこを触ってもうえっとならない)
慢性疲労感の症状があったそうです。実は口呼吸が原因だったそうです。
18歳のアトピー性皮膚炎の子
口呼吸でした。
塗り薬と内服治療を受けていましたが、あまり改善がみられませんでしたが
3ヶ月間口呼吸対策をし鼻呼吸になってから綺麗な肌に改善
50歳代女性
関節リウマチ
掌や足の裏に嚢胞が出来る皮膚病(金属アレルギーとの関連がいわれています)
扁桃腺摘出手術を行うと治る場合があります。
人間の鼻と口の奥は、ワイダイエルのリンパ輪といって外的から体を守る
リンパ組織が備わっています。ここに絶えず炎症が起きると(たとえば慢性扁桃炎)
免疫異常が引き起こされます。慢性扁桃炎から引き起こされた免疫異常がこの50歳女性の
場合皮膚に症状が現れた例です。
これを難しい言葉で(病巣感染症とも)いいます。
病巣疾患とは「身体のどこかに限局した慢性炎症があり、
それ自体はほとんど無症状か、わずかな症状に過ぎないが
遠隔の諸臓器に、反応性の器質的および機械的な二次疾患を起こす病像」
小さな症状のない炎症が、他の臓器にその炎症を飛び火のように持っていってしまうわけです。
口呼吸が原因だとは![]() 、、、怖いですね
、、、怖いですね
口呼吸から鼻呼吸へ、呼吸をもう一度見直し健康生活おを送りたいものです。


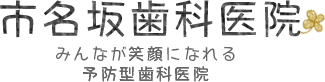
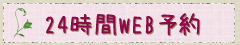
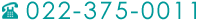
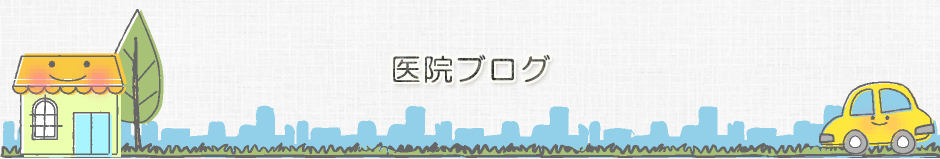

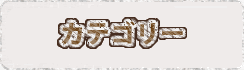
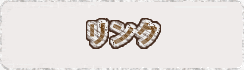


.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)